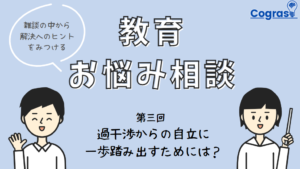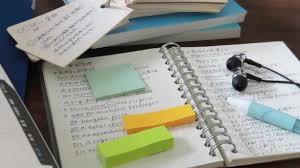学校の授業や宿題で出される調べ学習。
皆さんご存じの通り、調べ学習とは、自分でテーマを決め、必要な情報を集め、それを整理し、最後に発表やレポートにまとめる学習方法です。
しかし、調べ学習を進める中での困りごともありますよね。
テーマ選びに迷ったり、集めた情報の整理に苦労したりすることもあるでしょう。
そこでこの記事では、調べ学習をスムーズに進めるためのステップと、よくある困りごとの解決策を紹介します。
調べ学習のステップ、「テーマ決め」「情報収集」「まとめ」について、それぞれ解説していきます!
ステップ1:テーマを決めよう
調べ学習の第一歩は、テーマを決めることです。
ここで重要なのは、調べたいと思うテーマを選ぶことです。
自分が興味がないテーマでは、調べる気も起きませんよね?
とはいえ、興味があるテーマといわれても、すぐに思いつくものではないでしょう。
例えば、以下のようなお悩みはありませんか?
- 興味のあるテーマが見つからない
- テーマが広すぎて絞り込めない
- テーマは思いついても、まとめられるイメージがわかない
そんな時は、下の解決策を参考にしてみてください!
- ほんの少し気になったことを深堀りしてみる
趣味や日常で興味を持ったことからテーマを選びましょう。SNSやニュースで流れてきた情報、電車や街中の広告やCMなど、ヒントはたくさんあるでしょう。 - テーマを具体的に絞り込む
「地球温暖化」などの大きなテーマではなく、「地元でのリサイクルの取り組み」「」など、狭い範囲に絞ると調べやすくなります。 - 生成AIの活用
ChatGPTやGoogle Geminiなど、生成AIに面白いテーマがないか聞いてみるのも楽しいかもしれません。
ステップ2:どうやって調べるかを考える
次に、どうやって情報を集めるかを決めましょう。
どんな情報が必要かを考える
情報収集を始める前に、どんな情報が必要かを考えましょう。
こうすることで、情報の集めすぎるのを防いだり、最終的にまとめやすくなったり、良いことづくめです。
ここでは、以下のステップで考えてみてください。
「縄文時代の人はどんな悩みを持っていたんだろう?」「ダンゴムシはどうして丸くなるんだろう?」のように、テーマを疑問形にすることで、どんな答えを探せばよいかイメージしやすくなります。
たとえば、「縄文時代の暮らし」と「今の暮らし」を比較して、今の人が抱えている悩みが縄文時代にも当てはまるのか、暮らしの違いから悩みを推測してみるなど、何かと比べてみると良いですよ。
STEP2で考えた予想から、「きっとこれが答えだ!」という仮説を立てて、それを証明するように情報を集めてみると、どんな情報が必要かイメージしやすくなります。

いよいよ情報収集!
主な調べ方は、図書館で辞書や図鑑、新聞、雑誌を使ったり、インターネットで検索したりなどでしょう。
集め方について、下にまとめておきます。
- 図書館を活用する:図書館の本や雑誌は信頼性が高いです。司書さんに相談しておすすめの本を紹介してもらいましょう。
- インターネットの信頼できる情報源を使う:政府や教育機関のウェブサイト、または専門のブログや記事が役立ちます。Wikipediaも便利ですが、参考にする際には他の情報源でも裏付けを確認しましょう。
- インタビューも取り入れる:家族や地域の専門家に直接話を聞くと、生きた情報を得られます。
情報を集めるときのポイント
インターネットや書籍で集めた情報が信頼できるかどうかを確認することも大切です。
他にも、用いる情報ソースは一つではなく、なるべくいろいろな媒体や資料を調べるのが原則です。
限られた情報ソースに頼ってしまうと、偏った意見になってしまう恐れがあるためです。
とはいえ、情報を整理するなかで、以下のような困りごとに出会うこともあると思います。
- 信頼できる情報かどうかが判断できない:インターネットの情報は多種多様で、どれが正しいか迷います。
- 情報が食い違う:複数の情報源で違うことが書かれている場合、どれを信じればいいかわからなくなる。
そんな時は、以下の解決策を参考にしてみてくださいね。
- 公的な機関や実績のある人物が出している情報源を優先する
政府機関、大学、著名な学者の出版物やサイトは信頼性が高いです。SNSや個人ブログは慎重に扱い、裏付けを取ることが必要です。 - 情報を比較して正しいものを選ぶ
複数の情報源から同じ内容が確認できる場合、その情報の信頼性は高いです。異なる場合は、どちらの情報が新しいか、根拠がしっかりしているかを確認しましょう。 - 情報が対立する場合でも、両方とも正しい可能性を考える
集めた情報で反対のことを言っているものがあった場合は、前提条件が違っていたりして、両方が正しいことがある点を考慮しましょう。
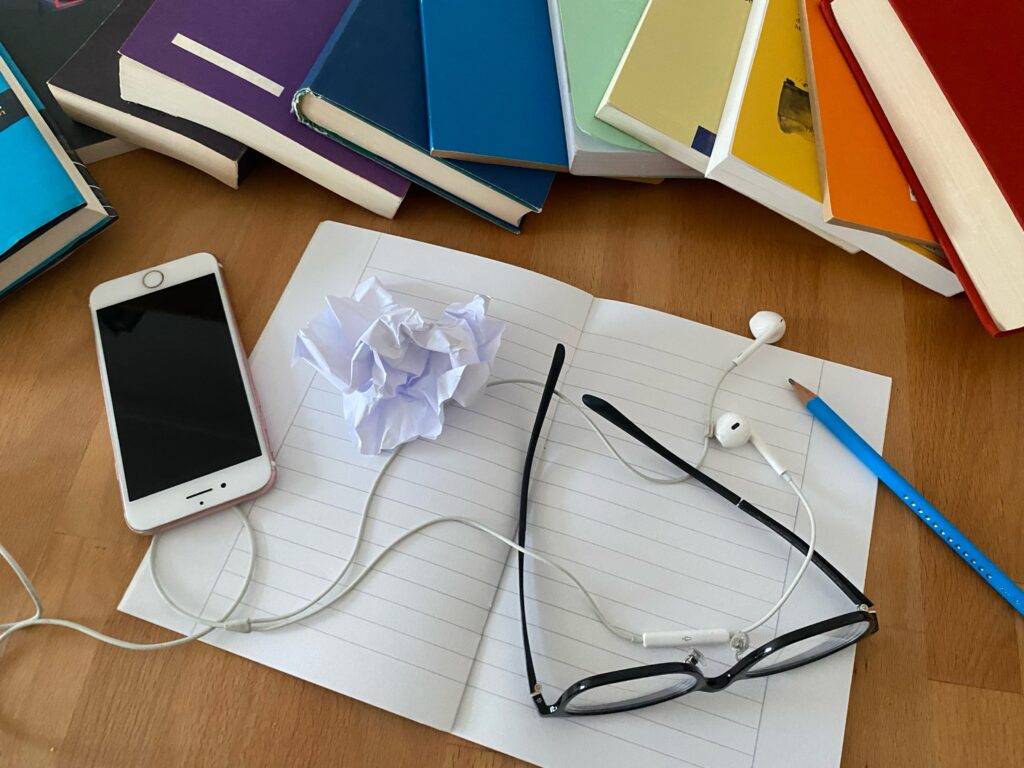
ステップ3:調べたことをまとめる
さて、いよいよまとめる作業です。
これまでの成果をしっかり伝えられるようにまとめるには、どのように考えると良いのでしょうか?
まずは、なぜそれを調べようとしたのか、何に興味があって、どこを疑問に思ったのかをまとめましょう。ここでは、最後は「以上の理由から、○○について明らかにしていく」のように、どんな謎を解明したいのかをしっかり伝えましょう。
どんな資料をつかって、どんなことを考えながら調べたのかをまとめましょう。ここをしっかりまとめると、調べたことの信頼性を高めて、より内容が伝わりやすくなりますよ。
STEP1の最後に書いた謎を解明できるように、調べた内容をまとめていきましょう。ここでは、参考にした資料の数字や文章を引用したり、自分でやった実験結果を書くと、より説得力が増します。
調査結果ですべての謎が解明できれば良いですが、そうではないと思います。そんな時は、「こんな謎が残っていて、それはこうやったら解明できると思う」であったり、「今回調べてみて、考えがこう変わった」のように、自分の感想や今後の希望についてまとめましょう
その他、調べ学習のコツ
ここでは、調べ学習を進める際に役立つコツをまとめます。
困ったことがあれば、参考にしてみてくださいね。
調べ学習をする意味
私は、何事も、「面倒だけど仕方なくやる」より「自分のためになるからやる」ほうが身になると考えています。
皆さんにとってもしかしたら面倒な「調べ学習」も、しっかり意味があるからやっているんです。
ですので、最後に調べ学習を学ぶ意味を話していきます。
わかっている、やる気満々だという方は、飛ばして大丈夫ですよ。

学び方を理解できる
ここまで説明してきた調べ学習のステップ、実は、他の勉強の仕方と同じなんです。
目的を設定して、その学び方・調べ方をイメージして、計画を立てて学習する。
調べ学習の流れは、普段の勉強ともつながっています。
また、こういった経験を通して、自分で情報を探し出し、考えをまとめる力を養うことができるため、これからの人生全体につながっていきます。
調べ学習はただ知識を増やすだけでなく、自分の意見や考えをしっかり持つことを学べる機会でもあります。
せっかくの機会なので、積極的に楽しんでいきましょう!
まとめ:調べ学習を通して学ぶ力を身に着けよう!
調べ学習を通じてさまざまな力を身につけることができます。
情報を集める力、整理する力、自分の意見を考える力など、調べ学習を続けることで大きな成長が期待できます。
失敗を恐れず、どんどん挑戦することで、新たな発見や学びをつかんでいきましょう!
投稿者プロフィール

最新の投稿
 教育ニュース2024年10月23日高卒採用ってどうなの?高卒就活の独自ルールを解説!
教育ニュース2024年10月23日高卒採用ってどうなの?高卒就活の独自ルールを解説! お役立ち情報2024年10月23日最速で成績を上げる方法をご存じですか?WBS式 学習効率化のススメ
お役立ち情報2024年10月23日最速で成績を上げる方法をご存じですか?WBS式 学習効率化のススメ お役立ち情報2024年10月22日調べ学習、自由研究をどう乗り越える?ネタ探しからまとめ方まで大解説!
お役立ち情報2024年10月22日調べ学習、自由研究をどう乗り越える?ネタ探しからまとめ方まで大解説! お役立ち情報2024年10月17日YouTube投稿しました!【第3回 家庭から自立をするためには?】
お役立ち情報2024年10月17日YouTube投稿しました!【第3回 家庭から自立をするためには?】